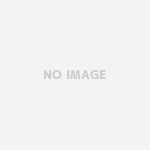(農業)(科学)
植物や動物に含まれる色素成分にカロテノイドがあり、その中にビタミンA作用をするα(アルファ)カロテン、β(ベータ)カロテン、クリプトキサンチンがある。このうちビタミンA作用が最も強いのはβカロテンである。βカロテンには、有害な活性酸素から体を守る抗酸化作用や、免疫を増強する働きもある。
分子式はC40H56。この同じ分子式で異性体がαカロテン,βカロテン,γ(ガンマ)カロテン…のようにあるが混合物になっていることが多く、総称してカロテンということもある。
かつてはカロチンともいった。
植物からつくられるが動物からはつくられない。
ニンジン(carrot)の色素でもあり、これがカロテンの語源になっている。ニンジン以外では、タンポポの花、カボチャやトマトの果実、サツマイモ、マスクメロンなど多くの果物や野菜に含まれる。枯れ葉の橙色(だいだいいろ)や、乳脂肪、バター、卵黄の黄色もカロテンによる。黄、橙色、オレンジ、赤もしくは赤紫色の色素となる。
動物では、脂肪、卵黄、羽毛、貝殻などにみられる。
βカロテンを含む緑黄色野菜の摂取は、生活習慣病などの罹病(りびょう)リスクを下げるとされる。