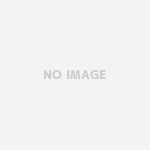(農業)(科学)
①「一日のうち明るい時間」
が簡単でわかりやすい定義である。
②「日の出から日の入りまでの時間」
とした定義では天候や日食による日々の明るさの変化は関係ないことになり、①と②は異なる。
③「日照時間の長さ」
をDay Lengthの日本語訳としている文献もある。これは②の日の出から日の入りまでという定義とは異なる。それは日照時間の定義が「一日のうちで、日照計で測定される直達日射量が120W/m2以上である時間」だからである。ここでは天候その他による明るさの変化が加味され、また山間部などの地理的要因の影響も加味される。この定義は①に近い。
※日長という言葉が使われるときは長日植物、短日植物、光周性の説明のときが多い。そこでは、ある1日だけの明るい時間や日照時間の長さを問うのでも、平野部と山間部で平均してどちらの日照時間が長いかを問うのでもない。1年を通して日の出時間、日の入り時間が変わることで昼の時間の長さ、夜の時間の長さが周期的に変わっていくことに論点がある。
※また、長日植物の定義では、日が長くなることよりも夜が短くなることが花芽形成の主因とされるので、1日24時間から日の長さを引いた夜の長さをも意味する定義を下記に用意した。
④「1年を通して周期的変わっていく日の長さまたは夜の長さ」。
※日長を要因とする植物の反応を感光性(かんこうせい)といい、温度を要因とする植物の反応を感温性(かんおんせい)という。
もしも出題で、
Q:「1日のうち明るい時間を( ① )といい、作物が日長に応じて花芽分化し、開花する性質を( ② )という。この( )にあてはまる言葉を答えよ。」
とあれば、その答えは、
A:①日長、②光周性、となる。