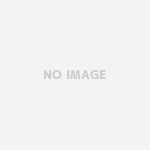(農業)(植物)
花の着きかたのこと。栽培のしかたや環境によって変わるものもある。
着花習性と花序という用語の違いは、着花習性は花が植物のどこに着くかをいうのに対し、花序は花の並び方をいうところにある。
例えば、「○○という植物は第1花が○節目に着く」というのが着花習性的な表現である。
着花習性の例
| ※ナス科植物
第1花房もしくは第1花は、8~9節目に着生するのが普通。 |
|
| トマト | 3葉ごとに着生する。 |
| ナス | 2葉ごとに着生する。 |
| トウガラシやピーマン | 1葉ごとに着生する。 |
| ※ウリ科植物
雌花、雄花の単性花に分かれていて(雌雄異花)、着花習性が複雑である。 |
|
| キュウリ | 雌花は普通1~2節に1花を着生し、雄花が数花着生する。温度や日長に強く影響される。 |
| スイカ、カボチャ | 主茎と第一次側枝の第6~8節に第1雌花が、以降4~6節おきに雌花が着生する。その他の節には雄花が着生する。 |
| メロン | 両性花と雄花を同一株上に着生するのが一般的で、普通は主茎に着生せず、主茎の第4~5節より上の節から発生する第一次側枝の第1節に両性花または雄花が着生する。 |
| ※マメ科植物
各葉の腋部に着生する。 |
|
| エンドウマメ | 主枝の第1花は、10~20節目に着生する。 |
| インゲンマメ | 主枝の第1花は、は5~10節目に着生する。 |
| ソラマメ | 主枝の第1花は、15~20節目に着生する。 |
| ※バラ科 | |
| イチゴ | 花が房状に着生し、頂部に頂花房、そして各葉の腋部にある第一次側枝の頂部に腋花房が着生する。
品種によっては第一次側枝上の葉の腋部よりさらに側枝を生じ、その頂部にさらに腋花房が着生するものもある。 |