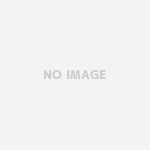(農業)(土壌)
群馬県赤城山の噴火によって地表に堆積した火山砂礫で、赤城火山をかなめにして東方に扇形に分布し茨城県にまで及ぶ。
土と呼ばれているが実際には軽石である。
成分は、長石、角閃石、カンラン石など。
直径数mm程度だった丸みを帯びた軽石が風化、団粒化し、アロフェンやイモゴライトが生成している。
有機物を含まない。
薄黄色を呈し、水を含むと鮮やかな黄色に変わるため、土壌の乾燥が判断しやすく水やりの目安にできる。
表面の毛管孔隙に空気や吸収した水分などを含むので、普通の畑土の2~3倍の保水性を持ち、排水性も優れている。
一度給水すると数日間保水し、粒子間のすきまが大きいため通気性がよい。
通気性、保水性の高さ、強い酸性度から、サツキなどのツツジ科の植物や東洋ランなどの栽培に向いている。
サツキ、ツツジ類には鹿沼土単独で用いる。
排水性に優れるため盆栽にも向く。
雑菌をほとんど含まないため、挿し芽、挿し木などにも適している
他の用土と配合して山野草(さんやそう)のためにも使われる。
松柏や多くの雑木類など酸性に弱い植物には向かない。
鹿沼土以外の浮石の堆積(たいせき)層は、九州南部の桜島周辺に分布する「ぼら」、長野県南部の「味噌土(みそつち)」などがある。
(*Pumiceの発音はpʌ́mis(パミス)。ピューマイスではない)(英訳をKanuma Soilとした文献はあるがおそらくKanuma Pumiceのほうが適切)
もしも出題で、
Q:「鹿沼土は、アルカリ性の性質をもち、ツツジの栽培に適している。」といったらこれは○か×か。
とあれば、その答えは、
A:×(鹿沼土はアルカリ性ではなく酸性。出題文でアルカリ性のところを酸性に変えれば○になる。)