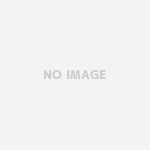(農業)(農法)
連作(れんさく)は、同じ圃場に同じ作物を続けて栽培すること。
輪作(りんさく)は、同じ圃場に違う作物を周期的に(本来は一定の順序で)栽培すること。
連作でなければ輪作であるという相反的な関係。しかし単年度にムギ―ダイズという2種類を栽培してこれが複数年繰り返されるときは多毛作型連作といって輪作ではない。また経済性で作付を決めていく自由式は一定の順序ではないので厳密には輪作ではないが、連作でないかぎり輪作的だといえるだろう。また連作、輪作、自由式の3つに分類してもいいがここでは連作と輪作の2通りにしてある。
連作も輪作も作付順序のあり方のひとつといえる。同じ作物を続けていくのが連作であり、違う作物を年度ごとに栽培するのが輪作である。
連作:作物A→作物A→作物A・・・。単年度に作物A→作物B、次の単年度にも作物A→作物B・・・。
輪作:ある年度に作物A、次の年度に作物B、次の年度に作物C・・・。
近年では連作の定義が単純(同一圃場に同じ作物)であることや、連作という用語の存在意義が地力低下や病害虫発生にあってこれを改善させるものが連作以外にあるという背景で、連作以外を輪作という傾向がある。
| 連作 | (連作)
同じ圃場に同じ作物を続けて栽培すること。 |
・土壌養分バランス悪化。
・地力低下。 ・病害虫増加。 ・毎年同じ時期に同じ作物を栽培すると病害虫が発生しやすい。 →連作障害 イネ科作物は比較的連作に強い。 マメ科、ナス科、キク科作物は連作に弱いものが多い。 |
| (多毛作型連作)
単年度に例えばムギ―ダイズを栽培してこれが複数年繰り返されるとき。 |
||
| 輪作 | 同じ圃場に違う作物を周期的に(本来は一定の順序で)栽培すること。 | ・地力維持。
・化学肥料や農薬の普及に伴い輪作の重要性は低下。 ・一定の作付順序で地力回復を目指すより、作物の市場価格動向(販売)や生産資材価格の動向(原価)で作付を決めることが増え輪作は以前ほどには意識されなくなった。 ・しかし環境保全型農業としては輪作は再度評価されている。 ・輪作の土壌効果に関してアーバスキュラー菌根が(作物のリン酸吸収に)関係しているという研究がある。 |
もしも出題で、
Q:「同じ作物を同じ畑に続けてつくることを( ① )といい、同じ畑に違う作物を一定の順序で周期的につくることを( ② )という。この( )にあてはまる言葉を答えよ。」
とあれば、その答えは、
A:①連作、②輪作、となる。
→連作障害