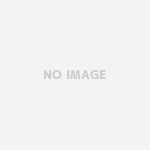(農業)(科学)
地表面に塩類が集積すること。これによって作物の収穫量が減る現象を塩害という。また塩類集積は砂漠化をもたらすことがある。
原因のひとつに干拓地や乾燥地における灌漑(かんがい)水に塩類が多く含まれていた場合の影響があげられる。
また、土壌中の水に溶けている各種の塩類が、地表面からの水分蒸発で地中水分が地表近くに移動しこれによって塩分が集積することがある。
塩類集積を避ける方法として、施肥を多くし過ぎないことがあげられる。全面施肥に比べ局所施肥のほうが肥料の利用率が高く、また環境に対する影響が小さいとされる。
塩類集積が発生した場合の対策として、湛水(たんすい)、深耕(しんこう)、客土(きゃくど)、吸肥力(きゅうひりょく)の強い作物を栽培して圃場(ほじょう)の外へ出すなどがあげられる。
露地栽培(ろじさいばい)では、降雨で土中塩分が流されるため塩類集積は起きにくい。施肥過剰の塩類集積が起きやすいのは降雨が地表に届かないようなハウス栽培である。
(耐塩性と作物)
| 耐塩性の強い作物 | ビート、オオムギ、ワタ |
| 耐塩性に関して中程度の作物 | イネ、ダイズ、コムギ |
| 耐塩性の乏しい作物 | エンドウ、インゲン |
*吸肥力の強い作物をクリーニングクロップ(Cleaning Crop)とした日本の文献が複数あったが、英語文献のなかには雑草地に適した作物をCleaning Cropとした定義はあるものの、吸肥力が強い作物というような定義づけは見つけられなかった。
*吸肥力の強い作物は、スーダングラス、ソルゴー、トウモロコシ、カボチャ、キャベツ、ソバ、ダイコン、トマト、ナスなど。