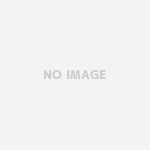(農業)(科学)
動物、植物の細胞や組織を無菌操作で培養すること。
培養とは動植物の一部を人工的に育てることをいうが、その中で組織培養とは多細胞生物の細胞や組織を人工的に育てることをいう。培養の対象に含まれて、組織培養の対象に含まれないものに、微生物(細菌、カビ、ウィルス(ただし細胞をもたない))がある。
多細胞生物でも、菌類や藻類など組織分化の程度の低い生物の培養は組織培養に含まれない(組織でないから)。
| 培養といわれるが組織培養とはいわれないもの | 微生物(細菌、カビ、ウィルス(ただし細胞をもたないので厳密には生物でない))。
菌類や藻類など組織分化の程度の低い生物。 |
細胞培養のとき、培養器具類や培養液(培地)類など接触するものを滅菌し、操作を無菌的に行なう。
組織培養には、動物の組織片をそのまま培養する器官培養(Organ Culture)と、動植物の細胞単位を培養する細胞培養(Cell Culture)がある。
目的は研究材料確保・疫学的調査・多量繁殖などである。
*Tissue(tíʃuː)は名詞で、1.薄い織物、2.〔細胞の〕組織、3.ティッシュペーパー(包装に使う薄い紙を含む)、という意味がある。