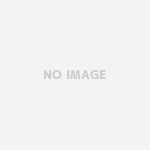(農業)(植物)
根(ね)と異なり、茎の地下部分であるところの地下茎の、4分類のひとつ。地下茎に多肉的な葉や鱗片葉(りんぺんよう)がつき、養分を蓄えているもの。
生育に不適な季節に地下に養分を保存して、芽や地下茎を守り、栄養繁殖器官にもなる。
鱗片葉とは、魚の鱗(うろこ)の形のような葉であり、芽を保護する芽鱗(がりん)や、タマネギのように地下茎をくるむようなものをいう。鱗片葉は形状による用語であり、付き方による用語ではない。魚の鱗の付き方と、タマネギのように地下茎の全周を同心円的にくるむような付き方は違うので、誤解せぬよう注意が要る。
また、ニンニクも鱗茎に分類されるが、タマネギやスイセンのように同心円的にくるむのではなく、独立的であり、リボルバーピストルの弾倉のような付き方であり、1葉1葉も鱗の形状とは異なっている(葉というよりナッツ類の形に似ている)。
| 作物の例 | タマネギ、ニンニク |
| 花きの例 | ヤマユリ、クロユリ、スイセン、チューリップ、ヒガンバナ、カタクリ |
| 雑草 | ヒルムシロ |
なお、園芸で球根(きゅうこん)とよばれるものの多くは、球茎でなくこの鱗茎である。