(農業)(科学)
肉眼で見えず、顕微鏡で見えるような生物。
生物を大きさによって分類した名称。厳密に0.0○mm以下のような定義はない。例として細菌、藻類(そうるい)、そして肉眼で見えるがカビ、ときとしてプランクトンなども含まれる。カビは、その集合体が肉眼で見えるが、構成単位は顕微鏡的な大きさである。
ウィルスは細胞(さいぼう)をもたないため生物でないとされるが微生物学で扱われる。
*この定義からすると、病原微生物には細菌、カビ、ウィルスがあるということになる。
Anywhere, Anytime when you want to know…
投稿日:2018年4月8日 更新日:
(農業)(科学)
肉眼で見えず、顕微鏡で見えるような生物。
生物を大きさによって分類した名称。厳密に0.0○mm以下のような定義はない。例として細菌、藻類(そうるい)、そして肉眼で見えるがカビ、ときとしてプランクトンなども含まれる。カビは、その集合体が肉眼で見えるが、構成単位は顕微鏡的な大きさである。
ウィルスは細胞(さいぼう)をもたないため生物でないとされるが微生物学で扱われる。
*この定義からすると、病原微生物には細菌、カビ、ウィルスがあるということになる。
執筆者:Aglay
関連記事
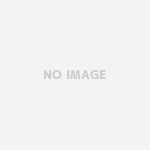
(農業)(科学) 無菌作業を行うための箱状のスペース。ベンチというと長椅子をイメージされてしまいがちだが、作業台・大工仕事や機械作業で用いる机・加工機械の加工品を載せる台をWorkbenchといい、英 …
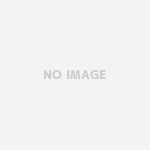
(農業)(科学) 熟成していく野菜や果物から発生するガス。成熟ホルモンと呼ばれる。果物の多くはこれによって果物に含まれる酵素の働きが促されて熟していく。そのため追熟(ついじゅく)用に足されることがある …
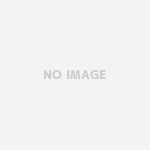
トマトの着果促進(とまとのちゃっかそくしん)(Fruit-Setting for Tomato, Fruiting Acceleration for Tomato*)
(農業)(科学)(農薬) トマトに限らず、ナス、メロン、モモ、ブドウなどにおいて着果性を高める薬剤を着果剤という。または着果ホルモン剤、植物ホルモン剤という。植物自ら作り出しているホルモンと同様の働き …
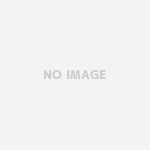
原生生物(げんせいせいぶつ)(Protist, Protozoa)
(農業)(科学) 真核生物のうち、①動物、②植物、③菌類(カビ(糸状菌)、酵母、キノコ)以外の生物の総称であり、それは④原生動物、⑤クロミスタ(藻類を含む)となる。 ④原生動物の例として、鞭毛虫類(ミ …
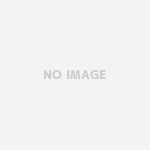
光合成(こうごうせい)(Photonic Synthesis, Photosynthesis)
(農業)(科学) 植物が太陽光のエネルギーを用いて、二酸化炭素と水から有機物(炭水化物)を合成し、酸素を放出する反応。 CO2+H2O→(CH2O)+O2という化学反応で表される。 明反応と暗反応に大 …